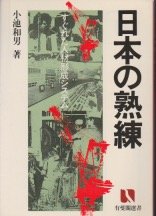後姿探検隊
ーーーー
「幸福塾」は、「日本への回帰」の2回目。取り上げた人物ーーー日下公人・芥川也寸志・高橋龍太郎・水木しげる・山本周五郎・鈴木大拙・渡辺京二・梅棹忠夫・渡部昇一・・寺田小太郎・石川九楊・吉田直哉・網野善彦・白洲正子・森嶋通夫・大野晋・長部日出雄。
以下、塾生の学び。
- 本日はがらりと変わって、図解プロセッサーで「名言との対話」その他の情報を読み込ませて図解にしたものを見せていただきました。驚くべき進歩で、少し前までは決まったパターンの図しか出てこなかったのですが、今日のはそれぞれに相応しいレイアウトで出力してくれてました。日下公人、芥川也寸志、鈴木大拙、渡辺京二、渡部昇一、網野善彦、白洲正子、森嶋通夫、長部日出雄、寺田小太郎、吉田直哉、大野晋、山本周五郎、高橋龍太郎、水木しげるが紹介されていました。改めて感心したのは仕事量。水木しげるは原稿料の半分を資料収集に使うなど徹底した資料収集、山本周五郎は読書のため以外の時間は無い、などが印象に残りました。 今後もしっかりした資料の収集と図解コミュニケーションの深い理解、プロンプトの指示を始めAIとの付き合い方を極めることを身に付けることが大切だと思いました。
- 今日は久恒先生が書かれている「名言との対話」の中の人物論を「図解プロセッサー」で図にしたものを十数枚見せていただきました。「図解プロセッサー」に文章を読み込ませて描いた図は、文章のキーワードが、図解塾でよく使っている⬜︎や◯、吹き出しなどでくくられ、文章の流れや構造が、とてもわかりやすく表現されているのに驚きました。また、図解から文章を書くこともできるのだそうで、これも驚きです。図解と文章をプロセッサーで行ったり来たりできそうで、とても興味が湧いてきます。例えば、手書きで描いた図解とプロセッサーで描いた図解の比較であるとか、文章→図解→文章とやったときに、元の文章と、図の後に書いた文章とが、どんな違いになるのか(あるいは同じ文章が出てくるか)見てみたいとも思いました。 また、今日の図解で出てきた人物論で印象深かったのは渡辺京ニと網野善彦。どちらも日本の歴史の教科書にはあまり出てこない独特の視点や研究対象を持っているところが面白いと思いました。来月からは図解プロセッサーを実際に使ってみるところまで行けそうで、とても楽しみです。引き続きよろしくお願いします。
- 久々に参加させていただきました。ありがとうございました。日本には偉大な人がいるのだとしみじみ。図解で示してもらえると要点がすっと頭に入ってきます。図で覚えるので、要点を忘れないように思います。その図解がプロセッサーでできたとしたら、すごいですね。お話を聴いてから、今日までかなり進化してきました。どこまでいくのか楽しみでしかないです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「名言との対話」6月18日。小池和男「知的熟練」
小池和男(こいけ かずお、1932年7月18日 - 2019年6月18日)は、日本の労働経済学者。享年86。
新潟県出身。労働経済学専攻。1960年、東京大学社会科学研究所助手。1963年、経済学博士。1963年、法政大学経営学部専任講師、のち助教授。1970年、名古屋大学経済学部助教授、のち教授。1981年、京都大学経済研究所教授(比較産業研究部門、1986年4月より比較経済研究部門)。1986年10月、京都大学経済研究所長事務取扱、1987年、同研究所長。1988年、法政大学経営学部教授。2001年、東海学園大学経営学部教授。2004年、法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授。
1979年『労働者の経営参加』でサントリー学芸賞、1988年『人材形成の国際比較』で大平正芳記念賞受賞、1996年に紫綬褒章受章。2009年『日本産業社会の「神話」』で読売・吉野作造賞受賞。2014年、文化功労者。
「欧米諸国でも内部昇進制や先任権制度があるから日本と変わらない、つまり日本は全然特殊ではないという議論」で、長く日本の労働形態を肯定的に捉えた論調をとった。日本的経営、特に日本型雇用システムに関する代表的な論客だった。徹底した聞き取りを武器に丹念に国際比較を行うスタイルは説得力があった。
私は29歳でJALロンドン時代に書いた社内レポート「ロンドン空港労務事情」を労働経済学の泰斗である名古屋大学の小池和男教授に送ったところ、中央公論に載せなさいと季刊「中央公論 経営問題」に紹介された。編集長と会い、社長から推薦をもらってくれるという話になったが紆余曲折があり、最終的には広報部次長の深田祐介主宰の企業の課長クラスの座談会で少しだけ紹介された。日本的経営を現場から論じた論文という位置づけだった。現場を研究すると時代のテーマとつながることがわかり、それ以来真面目に仕事に取り組む決意をした。1977年刊行の『職場の労働組合と参加』、1981年の『日本の熟練』をはじめ、この人の書籍をよく読み、自分のフィールドの改革と改善に役立てた。恩人の一人でもある。
2015年「文藝春秋」7月号では、「米国型『社外取締役』は無用の長物だ」という特集があり、優れたジャーナリスト東谷暁の一刀両断の摘発があった。このなかで紹介された小池和男著「なぜ日本企業は強みを捨てるのか」(日経)を手にしたこともある。この人は実に長く活躍した人物だ。
小池和男『「非正規労働」を考える』(名古屋大学出版会)を手にした。84歳の2016年5月刊行である。本人も「老い先短い」「老人」と自ら説明しており、2019年に亡くなっていることから遺言ともいえる。「はしがき」で「かつて働き盛りの時期に12年も勤めた大学の出版会」から出す幸運に感謝している。私が名古屋大学の小池研究室を訪問したのは、この時期だった。
本書では、製造業だけでなく第三次産業のサービス業についても丁寧に観察している。「非正規労働」にはそれなりの経済合理性があり、どの国にも存在し、戦後日本の1950年代、1960年代の大手製造業ではブルーカラーの半数が非正規だったと述べる。非正規には弊害もあるため全員を正規にする必要はなく、合理性を踏まえたうえで弊害をできる限り除去することが重要だと提言している。
また、多くの高度な非定常作業を担う中核的技能は非正規雇用では形成が難しいため、仕事表方式は無理であり、さまざまな体験をさせてじっくり育てるほかない。そのため労働組合の役割を高度な仕事を担うホワイトカラーにも広げ、専従者のサラリーを企業が負担すべきだと主張している。
本書の中で、非正規労働が4割近くまで増え続けている現状をどのように考えているかについては言及がなかった。小池和男は正規労働の中でも高度な仕事を担当する人たちに対する残業規制撤廃の動きを肯定しているように見える。また、近年出てきたジョブ型という仕事の割り当て方法は、小池の主張からすると、変化とトラブルへの対処という高度な仕事には知的熟練が欠かせないため馴染まないであろう。
主な修正箇所
-
句読点の統一・追加
- 「1960年 、」→「1960年、」など、カンマや句点の追加・削除で読みやすく修正。
- 「(比較産業研究部門 1986年4月より比較経済研究部門)」→「(比較産業研究部門、1986年4月より比較経済研究部門)」などカッコ内の読点追加。
-
表記の統一
-
言葉遣いの修正・明瞭化
- 「日本の労働形態を肯定的にとらえた論調をとった」→「肯定的に捉えた論調をとった」
- 「…手にしたこともある」→「…を手にしたこともある」など語順調整。
- 「この度」→「このたび」など日常的な表記に変更。
- 「…仕事表方式は無理であり…」→「仕事表方式は無理であり…」:「仕事表方式」という専門用語はそのままに文章を自然に。
-
誤字・脱字修正
- 「どのように考えているのだろうか、についてはわからなかった」→「については言及がなかった」など冗長表現を簡略化。
- 「さまざまな体験をさせてじっくりと育てるほかはない」→「じっくり育てるほかない」など冗長表現を簡潔に。
-
読みやすくするための改行など
- 段落のまとまり、適宜一文が長すぎる部分の分割等。